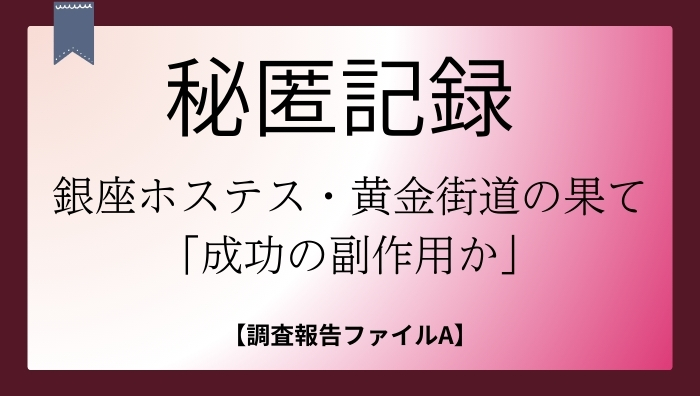
【真偽不明の秘匿記録】銀座ホステス・黄金街道の果て「成功の副作用か」【調査報告ファイルA】
リアル体験【閲覧注意】 衝撃のラストに耐えられる人だけ読み進めてください! 第1部成功の裏側煌びやかな日常の中で静かに「壊れていく」もの これはフィクションです。登場人物も、登場する場所全てが架空のものです。しかし実は…… 銀座という圧倒的華やかな富裕層向けの高級クラブで「最高の人生」を手に入れたはずの彼女たちだった…はずだった。しかし、それは見失ったものが彩られるほどに強烈なエンディングの始まりだった…。お金、男、自己肯定感…ではなく、自分自身を幸せにするための「感性」はどこへ行くのか。貴女は戦慄を覚えながら彼女たちのラストに震えるだろう…。 静寂(しじま)という名の天獄(てんごく) 詩織は、ショープレートの上に置かれたスプーンの歪みに映る自分の顔を見つめていた。32歳。銀座並木通り、クラブ『Z』のナンバークラス・ホステス。 「詩織ちゃん、これ、君の生まれ年のロマネ・コンティだ。どうだ?にくい演出だろう?」隣で初老の建設会社社長が、まるで自分の血液を誇るように赤黒い液体を注いでくる。1本200万円以上はする。グラスに鼻を近づける。 腐葉土とスパイス、そして微かな血の匂い。以前なら、この一杯で背筋が震えたはずだ。 「私は特別な女だ」という全能感が、アルコールと共に脳髄を駆け巡ったはずだ。 だが今は、ただの古い葡萄汁だ。 喉を通る液体よりも、社長の頬にある大きなシミの方が気になって仕方がない。 「……ええ、素晴らしい香りですわ。社長のおかげで、私も歴史の一部になれました」 口から出たのは、自動販売機のボタンを押した時のような定型文だった。心拍数は65から微動だにしない。最近、何を食べても、何を貰っても、このザマだ。エルメスの担当者が持ってくるバーキンの新色も、タワーマンションの夜景も、全てが色褪せた背景画に見える。 「…私の感覚は、あまりにも強い照明を浴びすぎて、焼き切れてしまったのかもしれない…。」 *** *** それから半年後、詩織は「上がり」を決めた。 相手は、店の上客だった大手総合商社の役員、高村だ。 誠実で、金払いが良く、何より詩織を「夜の女」としてではなく、一人の女性として尊重してくれる。 銀座中の女たちが嫉妬で狂いそうになるほどの、完璧な寿退社。引退の夜、黒服たちが並んで花道を作り、後輩たちが嘘泣きをする中、詩織は思った。 これでやっと、この渇きから解放される、と。 *** *** しかし、それが間違いだったことに気づくのに、三ヶ月もかからなかった。 港区の閑静な低層マンション。広すぎるリビング。 朝、高村を送り出し、ルンバがフローリングを這う音だけが響く空間。 詩織は、淹れたてのハーブティーを一口飲み、そしてシンクに吐き出した。 「……ぬるい」温度のことではない。 人生そのものが、致命的にぬるいのだ。 高村は完璧な夫だった。週末にはドライブに誘い、記念日には花束を贈る。暴言も吐かず、酒乱でもない。 だが、その「平穏」こそが、詩織の脳にとっては拷問だった。 銀座という戦場で、毎晩のように札束で殴り合い、男たちのプライドを綱渡りし、転落と栄光の狭間で脳内麻薬(エンドルフィン)を垂れ流してきた身体だ。 この穏やかな陽だまりは、彼女にとって酸素のない真空パックの中にいるようなものだった。 スーパーマーケットで、有機野菜の値段を見る。30円高いとか安いとか。 「馬鹿馬鹿しい…。」 私はかつて、一瞬の会話で数百万を動かしていた女だ。 それが今では、カボチャの鮮度を見極めている。 *** *** ある夜、高村とのディナーの席で、ふと発作が起きた。 高村が優しく微笑みながら、来週の休暇の予定を話している。 その穏やかな顔を見ているうちに、詩織の右手が、無意識にテーブルナイフを強く握りしめていた。(この綺麗なシャツに、赤ワインをぶちまけたらどうなるだろう?)(この人の会社の不祥事を捏造して、マスコミにリークしたら、どんな顔をするだろう?)背筋がゾクリとした。 久しぶりの感覚だった。 破滅。没落。絶望…。 かつて他人が落ちていく様を見て感じた、あのどす黒い快感が、今度は「自分たちの生活」を壊すことに向けられている。 *** *** 平穏な幸福が苦痛でしかない。脳が「毒」を欲しがっている。 リスクという名の劇薬を、喉が渇いて仕方がないのだ。 「詩織? どうしたんだい、顔色が悪いよ」 心配そうに覗き込む夫の顔。 詩織は、ナイフをナプキンの下に隠し、艶然(えんぜん)と微笑んだ。銀座で鍛え上げた、完璧な仮面を貼り付けて。 「ううん、なんでもないの。ただ、あなたが素敵すぎて……怖くなっただけ」嘘ではない。 私は今、あなたという人間を社会的に抹殺し、この退屈な城を火の海にする妄想で、久々にエクスタシーを感じているのだから。 夫が安堵の表情でグラスを傾ける。詩織はその無防備な喉元を見つめながら、自身の体内で何かが完全に壊れた音を聞いた。 私はもう、ただの人間には戻れない…。 成功という名の猛毒を食らった獣は、檻の中で餓死するか、飼い主を食い殺すか、その二択しかないのだと悟った瞬間だった。 脂の乗った魚体は太らせて食う 特上の大トロが、亜理沙の舌の上で体温により溶け出し、濃厚な脂の甘みを口腔内に広げる。 「どうだ亜理沙、美味いか?」 目の前でそう尋ねるIT長者の男は、亜理沙にとって財布であり、また彼女を輝かせるための舞台装置の一つに過ぎない。 亜理沙は喉を鳴らして脂を飲み込み、計算された十代のような笑顔を作った。 「最高ですわ。こんな美味しいお魚、私初めて」 嘘だ…。 銀座に来て三年、彼女の身体は最高級のタンパク質と脂肪だけで構成されている。 北海道から空輸された雲丹、フランス産の鴨、そして男たちが競って開ける高級ヴィンテージ・ワイン。 それらは全て、彼女という魚体を美しく、艶やかに太らせるための飼料だった。 亜理沙は、自分が「持っている」人間だと確信していた。 銀座デビューからわずか半年でNo.1の座を奪取。 客の嫉妬によるトラブルも、別の太い客が「面白い女だ」と庇ってくれて、逆に売上に繋がった。 まるで目に見えない飼育係が、水槽の水温も、餌の配合も、全てを亜理沙のために完璧に調整してくれているかのような、不自然なほどの全能感。 「私は選ばれたのだ」 エルメスのバーキンに無造作に放り込まれた札束の厚みを確認しながら、彼女はタクシーの窓に映る自分の顔に陶酔する。 肌には一点の曇りもなく、瞳は野心で濡れている。 今が一番、脂が乗っている。 *** *** *** 収穫の日は、嵐のような轟音と共に訪れたわけではない。 ある火曜日の午後、パサついたサンドイッチを齧っている時に鳴った、一本の電話が合図だった。 「……社長が、逮捕?」 その一言で、亜理沙の水槽のガラスは音もなく粉砕された。 頼りにしていたIT長者の巨額詐欺容疑。 連鎖するように、彼女の店の名義貸し問題、脱税疑惑、そして信じていたチーフマネージャーによる横領が発覚する。 昨日まで「ママ、一生ついていきます」と言っていた黒服たちは、蜘蛛の子を散らすように消え、残されたのは膨大な追徴課税と、違約金の請求書だけだった。 「助けて。誰か…。」スマートフォンを握りしめ、かつて彼女を崇拝していた男たちのリストをスクロールする。 コール音。コール音。コール音…。 そして留守番電話の無機質な電子音。 誰も出ない。その時、亜理沙は悟った。彼らが愛していたのは「亜理沙」という人間ではない。 「銀座で一番脂の乗った極上の魚」…だったのだ。 鮮度が落ち、泥がついた魚に、誰が高い餌を与えるだろうか? 運命という名の飼い主(飼育係)は、残酷なほど合理的だ。 丸々と太った彼女を網ですくい上げ、まな板の上に乗せた瞬間、興味を失って次の稚魚を育て始めたのだ。 「なんで……私が……」 マンションのエントランスで、差し押さえの赤紙を持った執行官の靴音が賑やかに近づく…。 その革靴のコツコツという音たちが、まるで包丁を研ぐ音のように聞こえて、亜理沙は耳を塞いでうずくまった。 *** *** *** 「いらっしゃいませぇー」ピンポ~んドアが開くたびに鳴る安っぽい電子ベルの音。 北関東の国道沿い。スナック『アリス』の店内には、古びたソファに染み付いたタバコのヤニと、激安の業務用おしぼりの甘ったるい柔軟剤の臭いが充満している。 亜理沙は、薄めた焼酎の水割りを客の前にドンと置いた。47歳。鏡に映る顔は、厚いファンデーションで目尻の皺を埋めているが、瞳の光はとうに失われている。 「ママ、今日も綺麗だねぇ。昔は銀座で凄かったんでしょ?」 作業着姿の客が、柿の種を齧りながらニヤニヤと笑う。亜理沙は、カウンターの隅に飾られた、色褪せた雑誌の切り抜きを指差した。 そこには、煌びやかなドレスを纏い、女王のように微笑む20代の自分がいる。 「そうよ。このドレスなんてね、一着500万もしたんだから。あの頃は、ビルの一つや二つ、すぐに買えたのよ」 「へえ、すごいすごい」客は全く信じていない様子で、適当に相槌を打つ。 亜理沙も、それが分かっている。分かっていて、語るのを止められない。 過去の栄光という残飯を反芻(はんすう)しなければ、今の惨めな味に耐えられないからだ。 焼酎のボトルに映る自分の顔が歪んでいる。 かつては大トロやフォアグラで満たされた胃袋に、今は酸化した揚げ油のような焦燥感がこびりついている。 ふと、有線放送から流行りのJ-POPが流れる。亜理沙はグラスに残った氷をガリリと噛み砕いた。 冷たくて、味がなくて、そしてどこか生臭い。 これが、食い散らかされた後の、魚の成れの果てだ。飼育係に見放された元・高級魚は、濁った水槽の底で、今日もエラをパクパクと動かして、来ない餌を待ち続けている。 続きを読む

